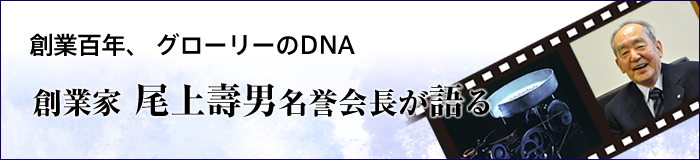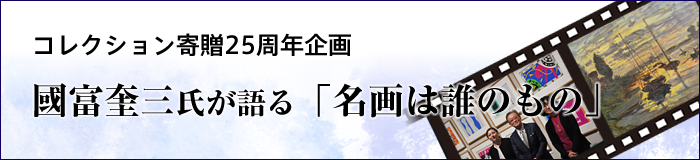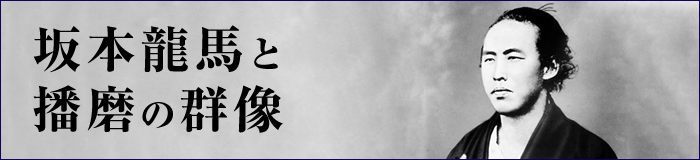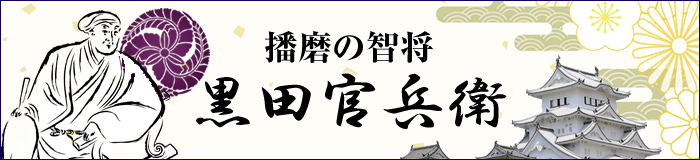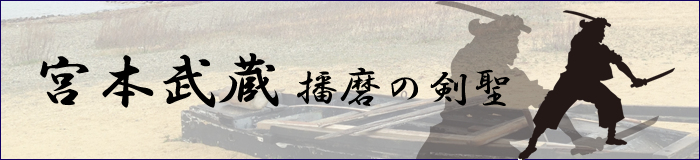幻の海城・英賀岩繫城
天下の名城白鷺城のある姫路から山陽本線を西へ下ると、その一つ目の駅に英賀保という小さな駅がある。
この駅は、かつて普通列車しか停車しない小さな駅で、急行列車に乗ったりすると、駅そのものがわからないまま通り過ぎてしまう。
また、鉄道地図などで英賀保駅の存在を知っていても、あがほと正確に読む人は少ない。それもそのはず、JRの全国珍名駅の中にこの英賀保駅が入っているのだから、正確に読めるのは鉄道通か地域の人に限られている。
私は少年時代、この地で過ごしたが、ドンコの列車が駅に到着すると、駅員が駅名を連呼しながらプラットホームを歩くのだが、その発声が奇妙で「アーホー、アーホー」と言っているように聞こえた。
全国の珍名にあげられる理由がこんなところからきているようだ。
しかし、こんな「アーホー」といわれる土地に、播磨の国有数の海城、英賀岩繫(あがいわつき)城(以下、英賀城)があったことは、一般に知られていないが、英賀保に住む人は知っていた。
城は駅から南へ一キロの地点にあった。
私の少年時代、往時を偲ぶにふさわしい土塁跡が残っていた。そしてその土塁に近い水田を掘ったとき、おびただしい数の人骨と赤錆びた刀片、武具類が現れたのを目撃した。
これらの水田からの出土品は、羽柴秀吉が英賀城を攻撃したとき、この城を死守しようとした武士のものであることは明白である。
しかし、天正八年(一五八〇)一月十七日、別所長治の三木城を攻め陥した秀吉が、中国の毛利攻略に兵を進める途上、意に従わぬ英賀城を攻撃して陥落させておきながら、どうしたことか史書には英賀城攻撃が登場しない。
一年七ヶ月という長期攻略を受けた三木城は、別所長治のドラマチックな死によって落城したことは、事細かに記されているが、短期決戦で落城させた英賀城攻めは、取るに足らぬ戦いとして処置したのか、勝利の証として城主の首級をあげることができず、その失敗を恥じて記録にとどめなかったのか。英賀城攻めは謎に包まれたまま葬り去られている。
これは勝者の手落ちを隠蔽したとも受けとれるが、これに対し敗者の英賀城側は、敗れたとはいえ、善戦したその記録を残している。英城記と英城日記というのがこれで、この記録は古い格式のある英賀神社に保存されてある。〈つづく〉
〈みき・こうへい〉
1923年(大正12)姫路市に生まれる。立正大学中退後、応召。46年中国から復員。阿部知二の門をたたき、「仲間」同人に。公務員、学校教師、ルポライターを経て、アジア文化研究所を設立。以来国内、アジア諸国を歩き、執筆活動に従事。主な著書に「参謀辻政信・ラオスの霧に消ゆ」、ブルーガイドパシフィック「タイ」など多数。故人。