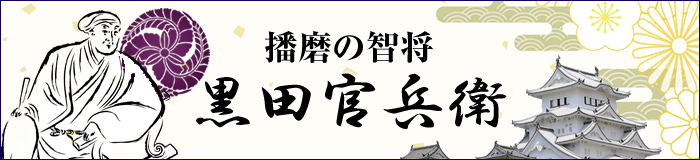文久二年(一八六二)、京都で起こった島田左近らの暗殺・梟首のうわさは、姫路へも伝えられたが、それは単に京都における現象とのみ考えられ、大きく藩論を動かすには至らなかった。
ところが翌年になると、長州勢力を中心に尊皇攘夷の動きはさらに高まりをみせる。名藩には渦中に飛び込んでいく脱藩浪士が増えていく。姫路藩もやがて無関心ではおれなくなり、開国・攘夷、尊皇・佐幕、両論が入り乱れて揺れ動き、やがて勤王党の台頭となるのである。
この年一月、姫路城下で藩御用達の商人「紅粉屋」主人の児島又左衛門が暗殺されるという事件が起こる。紅粉屋は町方六人衆の一人で、苗字帯刀を許されるほどの富豪だっただけに反響も大きかった。
姫路藩はかつて、七十三万両もの負債をかかえ、財政難にあえいでいたが、文化六年(一八〇九)時の家老、河合寸翁は藩政改革の一策として姫路木綿の専売制を取り入れた。大阪市場で買いたたかれる木綿を藩が独占的に江戸へ直送するというものだった。当時、江戸へ直送することは幕府方針にもとることだったから、姫路藩は幕府に働きかける一方、江戸問屋への根回しのため、紅粉屋の先代を江戸へ派遣、木綿問屋と折衝させた。江戸表における姫路木綿の専売権を認められた。以来、紅粉屋は藩と結んで、木綿の江戸積(専売制)を遂行する一方、藩の要請で飾磨港湛保の築造や新田開発に出資するなど功績が評価され、藩御用達六人のうちの一人として勢力を拡大していった。
幕末になると、紅粉屋は佐幕派の首席家老高須隼人ら守旧勢力との関係が強いということで、尊攘派ににらまれることになった。また、「紅粉屋は凶作に乗じて米の買い占めを画策した」などと噂されたり、庶民からも“悪玉”視されていた。
「奸商を尊皇討幕運動の血祭りに」。若い志士の間で計画が進んだ。
一月十二日、紅粉屋はわずかの供を連れ、網干・新在家付近の田地視察に出かけた。その帰途、橋之町にかかったのが四ツ半(午後十一時)。突然、暗闇の中からぱらぱらっと数人の武士が飛び出すと、「奸賊!」と叫びざま、供の小者が持った提灯を斬り落とし、又左衛門に斬りつけた。又左衛門を襲った暗殺団は、首をはねると、再びヤミの中へ。
下手人は藩の重役、境野求馬(番頭・五百石取り)の次男で、物頭、河合惣兵衛の養子となった伝十郎宗貞のほかに、江坂栄次郎行政、武井逸之助守正、永田弥四郎伴正、山口太藤平、出淵新吾、宇都木謹吾ら勤王党の七人。いずれも血気盛んな面々だった。
又左衛門の首を風呂敷に包んだ一行は、威徳寺町に住む又左衛門の愛妾おたきのもとを訪れる。「珍しいものを見せてやる」「真っ赤に熟れた天満スイカだ」と風呂敷包みを解いて差し出した。おたきは又左衛門の首とも確かめずに失神した。
威徳寺町を後にした一行は、大日河原で首をさらし、「米の買い占めをなし、庶民を苦しむにより天誅を加ふるものなり」と捨書して意気揚々と引き上げた。翌朝、小川橋の百姓がさらし首をみて驚天、紅粉屋へかけ込んだ。同家では、橋之町に打ち捨てられた死骸とともに引き取り、増位山随願寺へ葬ったという。この事件当時、城下には「蛸に骨なし、ナマコに眼なし、姫路紅粉屋に首がない」という俗語が流行った。
直接の加害者は江坂と武井。二人は、他に類がおよぶのを恐れ、自首して出る。ところが、藩庁では「罪は軽くないが、国家を思っての犯行で、特に憐憫の情をもって」と、裁判にもかけず、自宅謹慎を命じただけにとどめた。尊攘派への藩の仕置きは、まだ厳しくなかった頃であった。が、後になって厳しい裁可が下ることになる。
ところで、この事件の被害者は、長らく又左衛門とされていたが、最近発見された藩大目付の亀山雲平の手記から、児島家分家の又右衛門であることがわかった(姫路市教委歴史読本「姫路のあゆみ」)という。〈つづく〉
- ホーム
- ブログ
- 坂本龍馬と播磨の群像
- 第4回 河合伝十郎ら決起