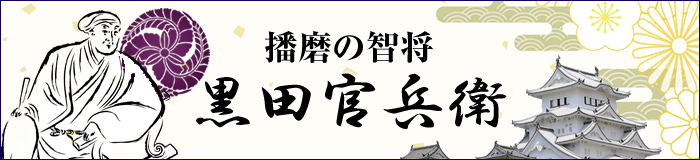慶応四年(一八六八)は姫路藩にとっても、「姫路」という地域にとっても記憶されるべき歴史的な転換点となった。関が原の戦の後、池田輝政が「西国への備え」として姫路城を建設してから二百五十年余。代々、徳川親藩の中でもとりわけ有力視されていた諸家が領有してきた土地だったが、この年を境に支配権が移ったといえる。江戸期最後の城主、酒井氏が幕閣の中枢にあったことで、討伐軍を迎えることになってしまった姫路藩。このことが新政府から“冷や飯”を食わされることになってしまうのだが、それは後の話。
約千五百の兵をもって真っ先に城を包囲した備前藩は福中町に宿陣を構えると、姫路藩に対し追討の令を伝え、帰順するかどうか、その去就を問うた。折から、藩主忠惇、隠居忠績はともに江戸にあって不在、意を確かめる暇もなかった。すでに譜代を含めて西国の諸藩はすべて恭順となっている。こうした状況の中で、譜代の雄藩姫路の動向が問われることになった。
姫路藩では直ちに国家老高須隼人以下が重臣会議を開いた。かつて佐幕派急先鋒として甲子の獄を断行した高須隼人は前年に病死、長男が家督を継承していたのだが、時流は如何ともしがたく、「恭順」は当然とも言える決断だった。人質を差し出し、城を明け渡すことしか選択肢はなかった。
ところが「平和的開城」の申し出に長州藩から横槍が入った。「酒井家は幕府主流。あくまで武力開城を」というのである。備前藩としても討伐の本軍が到着する前に城受け取りという方針を変更せざるを得なかった。戦闘準備を整えたうえで、景福寺山、男山上から城内に砲撃を加えた。これに対し、恭順の意を表していた姫路藩士たちは大きな驚きとともに、中には憤慨し、「さらば備前藩と一戦を交え、目にものを見せよう」とする徹底抗戦の動きも出始めた。しかし、朝敵の汚名をこうむることは何としても避けたい重臣たちはそれを押さえ、家老の大河内帯刀、藩主忠惇の一族である年寄酒井又七郎ら三人が討伐軍本陣へ出向いて降伏の書状を差し出し、自らが人質となり、兵器弾薬、兵糧など一切を引き渡すとともに、城明け渡しを申し出たのだった。
もともと姫路藩との戦争を望んでいたわけではなかった備前藩は、すぐに砲撃を中止し、藩士すべてに城外退去を命じた後、城を接収した。一月十六日のことだった。
城を追われた藩士たちは、それぞれ縁故を頼って行った。行き先のない者の中には田畑や市川河原で野宿するものもあった。寒中に夏の蚊帳を吊って寝る者もあり、哀れを極めた。剣術指南役細井市太夫のように市川敷で切腹して果てる者もあった。一方、町方も大変な騒ぎで、荷物を担いで逃げ出す者が相次いだという。
そうこうするうちに「禁門の変」の際に長州へ逃れた七卿の一人を総督とする討伐本軍が姫路に到着、事後処理が始まった。帰城を許されたのは十日後のこと。
ここで軍使応接役として登場するのが大目付亀山源五右衛門(雲平)である。この時四十七歳。〈つづく〉
- ホーム
- ブログ
- 坂本龍馬と播磨の群像
- 第11回 追討軍姫路城下に