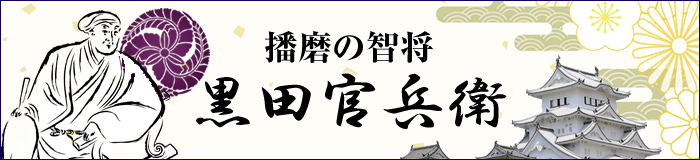「播磨不穏」の報に、安土を出発した秀吉は、天正六年(一五七八)三月四日、加古川城に入った。だがこの二、三カ月の間に官兵衛の働きかけで、織田方についていた播磨の情勢も一変してしまっていた。
毛利と織田を天秤にかけていた播磨の大名は、「毛利動く」の報に動揺、まず、三木の別所長治が反旗をひるがえした。別所一党の三木城にはきこえた勇猛の将、出城がある。播磨を足がかりに中国平定へ乗り出そうとする秀吉にとって進入口の謀反は大打撃であった。
別所氏寝返りの理由は何だったか。加古川城での軍議で、秀吉と別所方の意見に食い違いが生じたとの説があるが、一方で、毛利への寝返りを決めた長治は、風邪と称して出仕せず、叔父の執権、別所山城守賀相と家老三宅肥前守治忠を名代として伺候させていたという。
賀相は、別所の家系・軍功の長談義をして秀吉の不興をかったという。別所方は「筑前殿は、諸政横逆で恨みをもつものも多い」「土着城主の意見を入れない」などと信長へ書き送ったとしているが、これはこじつけ。実は「名門の別所が家柄のない秀吉ごときに」と自負し、播磨平定の暁には「信長は秀吉に播磨を与え、別所は滅ぼされるのではないか」と勘ぐっていたという。もともと秀吉の近くにいた同じ長治の叔父、別所永棟と賀相は仲が悪い。軍議の席での問題は理由にならないという説である。
毛利か織田かの葛藤の末に、毛利を選んだ別所は城郭の濠を深め、塀を高くして戦いに備えた。籠城軍はその数八千。播磨の一城主が集めうる最大の兵力である。ここに世の流れ、時の流れを見誤った地方豪族の悲劇が始まる。史上有名な「三木の干殺し」の幕開けである。
戦国史上、もっとも陰惨過酷を極めた籠城戦と伝えられる秀吉の三木城攻めは、天正六年から八年初めにかけての一年余におよぶ。
その三木城は、三木市の市街地が見える美嚢川の左岸、上の丸台地の先端に築かれている。鎌倉時代に赤松氏から分かれ、播州加西郡別所(現・加西市)を領有して別所氏を名乗った則治が十五世紀末に本格的な城郭を築いた。則治の曽孫に当たる安治は、永禄八年(一五六五)、信長が松永・三好の討伐軍を催したとき、弟の孫右衛門重棟に手兵三百を与えて上洛させており、重棟は二条大宮の合戦で軍功を上げたのがきっかけとなって信長の知遇を得た。安治の次弟が「別所を滅亡に導いた」などといわれる山城守賀相である。
安治が三十九歳で病没したのが元亀元年(一五七九)。嫡男長治はまだ十二歳の少年だったので、賀相、重棟の兄弟が後見役となった。これがそもそもの発端で、家内は二派に分裂、重棟は織田・秀吉びいきに、賀相は毛利へなびく。
反織田を決意していた三木方は、戦闘準備の時間かせぎをするため「城普請」の許可を信長に請い、直ちに城郭整備と兵糧の搬入にかかるとともに、東西播磨の諸将に回状を送って味方を要請した。七千五百余の将兵は、決死の覚悟で三木城に籠った。これには郡内十カ村の百姓たちも加わっている。
別所が反旗をひるがえすと、織田か、毛利かと様子をみていた東西播磨十一城の城主も呼応、反信長の旗幟を示した。淡河定範(美嚢郡淡河城)、中村景行(金山城)、梶原景行(高砂城)、長井政重(野口城)、櫛橋伊則(志方城)、神吉頼定(神吉城)と三木通秋(英賀城)などと、官兵衛には主家に当たる小寺政職(御着城)も。また、志方城の櫛橋伊則は官兵衛にとって義兄(妻の兄)であった。
事態の急変に驚いた秀吉、官兵衛らは、重棟をして何度も長治の翻意を促したが、長治はじめ三木方の意志は固く、不調に終わった。加古川の糟谷館にあった秀吉は腹背に敵を迎えるかたちになった。〈つづく〉
- ホーム
- ブログ
- 播磨の智将 黒田官兵衛
- (五)秀吉の播州征伐、始まる