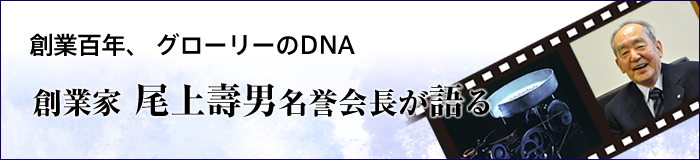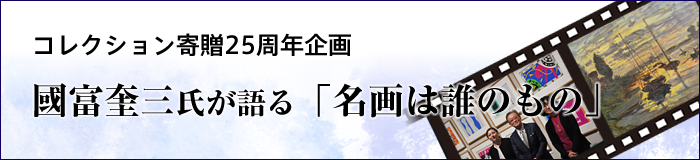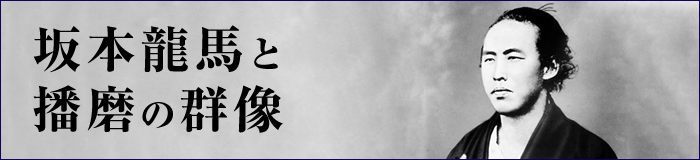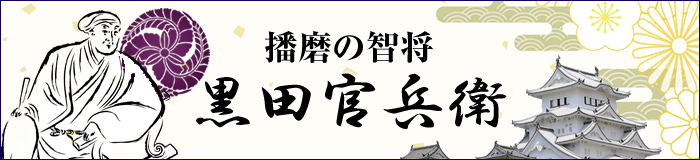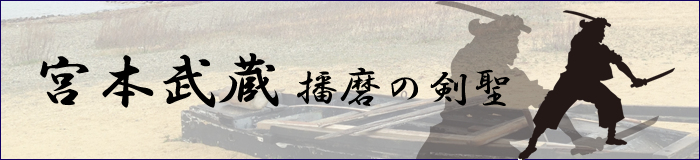慶長四年(一五九九)、武蔵は十六歳で但馬の兵法者秋山某と試合して勝ち、さらに京都に出ると、かつて足利将軍家のお抱え剣道指南だった吉岡清十郎を漣台寺野で破ります(慶長九年、二十一歳)。
さらに、その弟、伝七郎を伏見の蓮華王院で、清十郎の子又八郎を名代に立てた吉岡一門も洛北一乗寺下り松に倒して武名を高めたのです。
武蔵は工夫して二刀流を編み出し、「二天流開祖」となって諸国で試合、また真剣勝負をして、生涯を終えるまで、槍の宝蔵院と試合う(二十一歳)など六十余回戦って一度も敗れたことがなかったといい、無敵武蔵を豪語していました。
「五輪書」には、次のように書いています。「その後、国々所々に至り、諸流の兵法者に行逢ひ、六十余度まで勝負すといへども、一度もその利を失はず、その程、年十三より、二十八九までのことなり。三十を越えて、跡をおもひ見るに、兵法至極して、勝つにはあらず、おのづから道の器用ありて、天理を離れざるが故か、又は、他流の兵法不足なる所にや」
この間、関ヶ原(慶長五年九月、十七歳)や大坂の陣(同十九年、二十一歳)にも参戦しました。関ヶ原の合戦では西軍に加わり、敗戦後の厳しい落ち武者狩りから逃れて、九州にあった姫路ゆかりの黒田家を頼りました。このとき福岡城の築城に関わったのではないかともいわれます。
また慶長十七年(一六一二、二十九歳)、小倉城主細川忠興の剣道指南役、巌流佐々木小次郎と豊前小倉の舟島で勝負し、巌流のツバメ返しに対して急ごしらえの木刀で闘って倒したことはあまりにも有名です。この舟島の決闘を最後に、武蔵は血なまぐさい決闘とは無縁になります。〈つづく〉
- ホーム
- ブログ
- 宮本武蔵 播磨の剣聖
- 第4回 武蔵の諸国修行